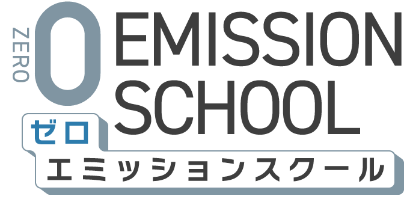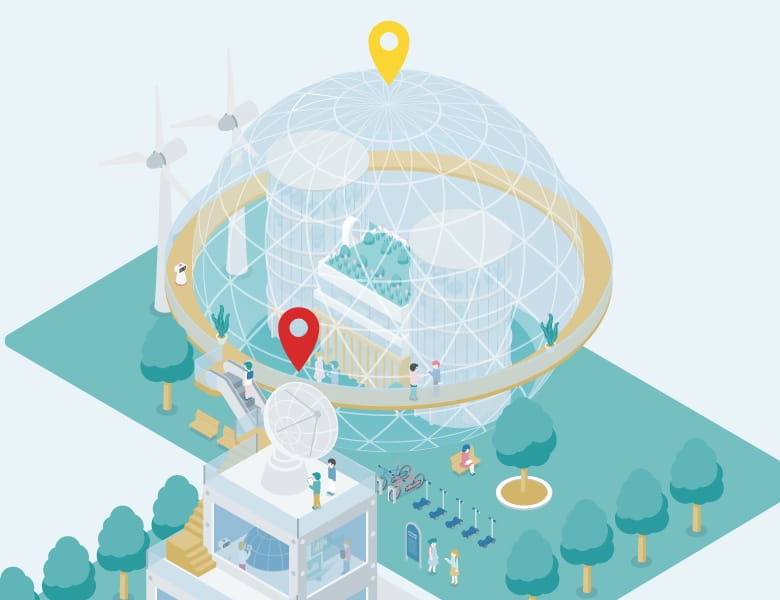オゾン層
オゾン層は、地上約10〜50km上空の成層圏にあり、オゾンという気体を多く含む領域です。太陽からの有害な紫外線を吸収し、地球の生態系を守る重要な役割を担っています。しかし、1970年代に人工化学物質であるフロンがオゾン層を破壊する可能性が指摘され、1982年には日本の観測隊が、オゾンが著しく少ない「オゾンホール」を南極上空に発見しました。その後、「ウィーン条約」や「モントリオール議定書」によりオゾン層を破壊する物質が規制されたことで、オゾン層の回復が進んでいます。将来的には完全に回復すると予測されており、これは国際社会が協力して環境問題に取り組んだ成功例として高く評価されています。